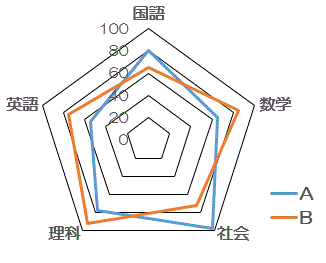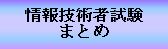��ƂƖ@��(2)
��Ɗ���
OR�EIE
 OR(Operations Research�F�I�y���[�V�����Y���T�[�`)
OR(Operations Research�F�I�y���[�V�����Y���T�[�`)
�o�c�ɂ�������̕��͂���������邽�߂̎�@
��Ƃ��o�c�v��𐔊w�I�E���v�I���f���A�A���S���Y���̗��p�Ȃǂɂ���āA���܂��܂Ȍv��ɍۂ��čł������I�ɂȂ�悤�Ɍ��肷��Ȋw�I�Z�@�B���w����уR���s���[�^�̉��p����Ƃ��Ĕ��W���Ă���
 IE(Industrial Engineering�F�C���_�X�g���A���G���W�j�A�����O)
IE(Industrial Engineering�F�C���_�X�g���A���G���W�j�A�����O)
���Y�����T�[�r�X�ɂ���������������邽�߂̎�@
��̓I�ɂ́A�l�E�@�B�E�ޗ��E�G�l���M�[�������悭�g�ݍ��킹�āu�������m�Â�����s���v���Ƃ��������邽�߂̋Z�p���w��
�z�����E�A�����
�z������Ƃ́A���Ȃ������ōő���̗��v�邽�߂ɁA�o�c�����̔z�����v�悷�邱��
�A������Ƃ́A���i�Ȃǂ�A������ۂ̉^�����ŏ����ɗ}���邽�߂ɁA���������甭����ւ̗A���ʂ��v�悷�邱��
 ���`�v��@(LP�@)
���`�v��@(LP�@)
�ꎟ�s�����ŕ\���ꂽ���������̒��ŁA�ړI�̒B���x���ő�ɂ���œK�̕��@�����߂鐔�w�I�Z�@�B�o�c�v��E�A���v��Ȃǂɗ��p�����
�ɖ��
��ɓK�ȍɗʂ�ۂ��ƂŁA��Ƃ̌o�c�̊�b���x���邱�Ƃ��ł��邽�߁A�ɂ��Ǘ������@���K�v�ƂȂ�
�o�ϓI������(EOQ)
�����̏��i���ɂ����āA����Ɋ֘A�����R�X�g�̑��z���ŏ������锭���ʂ̂��ƁB�܂��͂��̔����ʂ����肷���@�̂���
| �o�ϓI�����ʁF�Ɉێ���p�������ʁ@�ƂȂ锭���� |
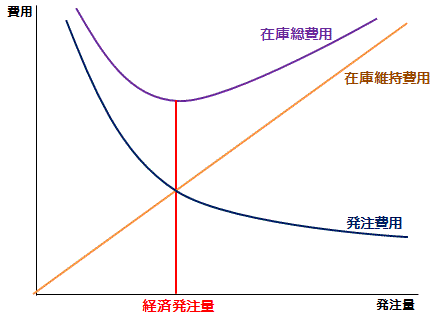
| ���� | ���� |
|---|---|
| ������p | �P��̔����ɂ������p�B�P��̔����ʂ�������A���������邽�ߔ�p�͌��� |
| �Ɉێ���p | �q�ɂ̊Ǘ���ȂǁB�ɐ��������A�ۑ����Ԃ������Ƒ������� |
| �ɑ���p | �Ɉێ���p�{������p |
| �o�ϓI�����ʂ̍l�����̑O�� �@�@�������R�X�g�����ł��� �@�@�����v�����������Ă��āA�N�Ԃ�ʂ��ĕ��ϓI�ɕ��U���Ă��� �@�@�����[�h�^�C�����Œ肳��Ă��� �@�@���w���P�����i����� �ȉ���2�̃R�X�g���ŏ������锭���ʂ��o�ϓI������ �@�@�������R�X�g�����v�ʁ������ʁ~1����̔�����p �@�@���ɕۊǃR�X�g��1������̕ۊǗ��~�����ʁ�2 |
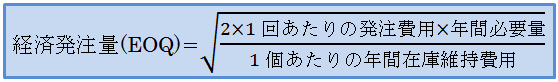
 �J���o������(�W���X�g�C���^�C�����Y�V�X�e��)
�J���o������(�W���X�g�C���^�C�����Y�V�X�e��)
�o�ό��������߂邽�߂̋Z�p�̌n(���Y�Z�p)�B�g���^�����Ԃ̐��Y����(�g���^���Y����)�̑�\�I�ȗv�f�Ƃ��Ēm����B�g�K�v�ȕ����A�K�v�Ȏ��ɁA�K�v�͂ȗʂ������Y����h����
 MRP(���ޏ��v�ʌv��)
MRP(���ޏ��v�ʌv��)
���Y�Ǘ���@�̈�ŁA��Ƃ̐��Y�v��B����O��ɁA���i�\�ƍɏ�甭�����ׂ������̗ʂƔ�������������o������
��������
 ��ʔ����_����
��ʔ����_����
���鐔�ʂ��ɂ����Ȃ��Ȃ�ƕK�v���ʂ��������
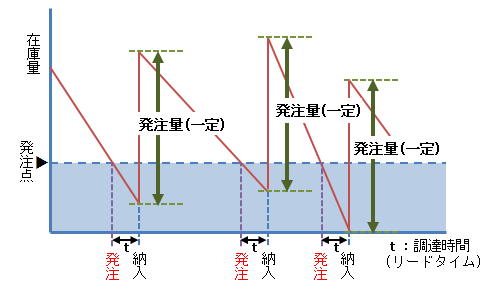
�������_
�@�@��������^�C�~���O�ƂȂ�ɗʂ̂���
�����S��
�@�@���v���ϓ����邱�Ƃ����z���āA���i��h�����߂ɗ]���Ɋm�ۂ��Ă�����
�@�@�̂���
���[�����[�h�^�C��
�@�@���i�����Ă���[�������܂ł̊��Ԃ̂���
| �����_��1��������̕��ϓI�g�p�ʁ~�[�����[�h�^�C���{���S�� |
 ��������_����
��������_����
���T1��Ƃ�1������1��Ƃ����߂�ꂽ�����Ԋu�ŕK�v�Ȕ����ʂ��v�Z���Ĕ����������
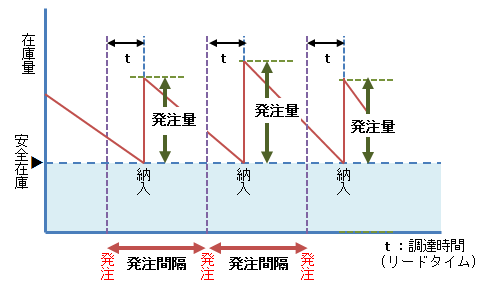
�ӎv����
�ӎv����Ƃ́A�s�m���ȏ����̂��Ƃɂ��Ă̈ӎv�����肵�A�o�c���j�����߂邱�ƂŁA��@�Ƃ��āu����\�v�u����v������
������\�F�����肪�^�����Ă���Ƃ��ɍl�����ׂ������Ƃ��̏����Ɋւ�����̂�����\�̂��ƁB�f�V�W�����e�[�u���Ƃ��Ă�
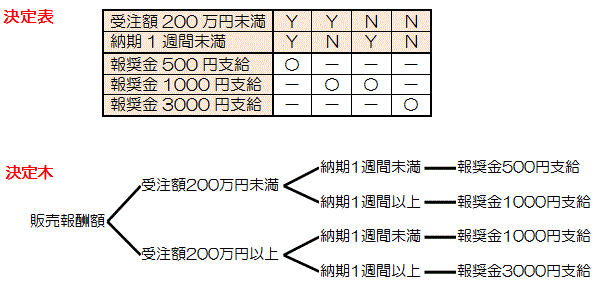
��Ƒ���
��Ƒ���Ƃ́AIE(�C���_�X�g���A���E�G���W�j�A�����O)�ɂ����āA�H��Ȃǂ̐��Y����œ����l�̍�Ƃ𑪒肷���@�ŁA���Y���C���̍H���̉��P��}��
| ���� | ���� |
|---|---|
| ��Ǝ��ԕ��͖@ | ��Ǝ��Ԃ̒����Ɏg�����@�B�X�g�b�v�E�H�b�`�Ȃǂ��g���āA���ۂ̍�Ɠ���𐔉�ɂ킽�蔽�����肵�A��Ǝ��Ԃ����� |
| PTS�@ | ��ƂɕK�v�ȕW�����Ԃ����ς���Ƃ��Ɏg�����@�BPTS�@�ł́A��ƂɕK�v�ȓ������{����Ƃ��ĕ�������B���̏�ŁA��{����̕W�����Ԃ���ɁA�\��������{����̎��Ԃ����v���č�Ǝ��Ԃ����߂� |
| ���[�N�T���v�����O�@ (�u�ԑ���@) | �ғ����͂Ɏg�����@�B�ϑ������߂āA�����_���ȏu�ԂɁA�����Ǝ҂̍�Ə��ϑ��A��Ɠ��e�≽�ɂǂꂾ�����Ԃ����������͂��� |
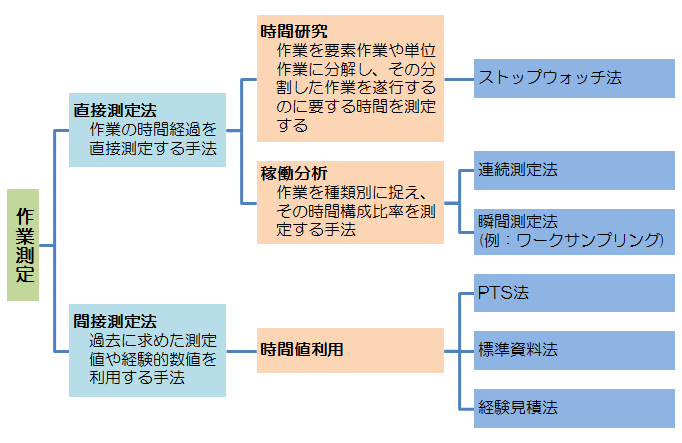
�i���Ǘ�
�i���Ǘ��Ƃ́A����҂̖�����ɑ��鍂�x�̗L�p����L���鐻�i���ł��o�ϓI�Ȑ����ɂ����Đ��Y���邽�߂̌v�����邱�ƂƁA���̌v���B�����邽�߂ɍs�����ׂĂ̊���������
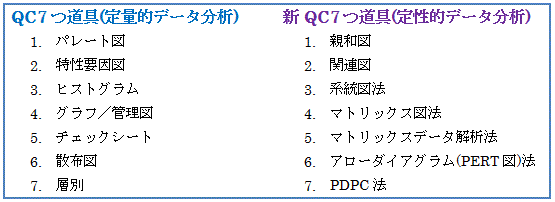
QC7����
 �q�X�g�O����
�q�X�g�O����
�o���c�L�̕��z��Ԃ�_�O���t�ŕ\�������́A�܂�f�[�^�̓x�����z���O���t�ɂ�������
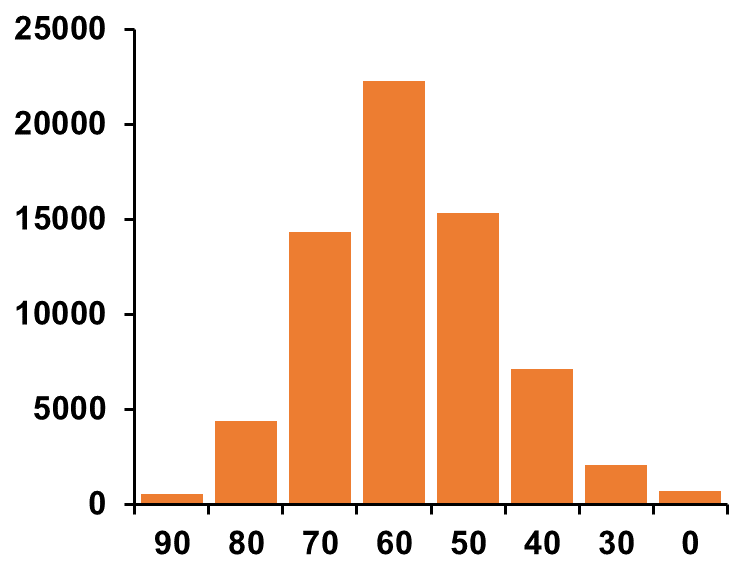
 �p���[�g�}
�p���[�g�}
�l���~���Ƀv���b�g���ꂽ�_�O���t�Ƃ��̗ݐύ\�����\���܂���O���t��g�ݍ��킹�������O���t
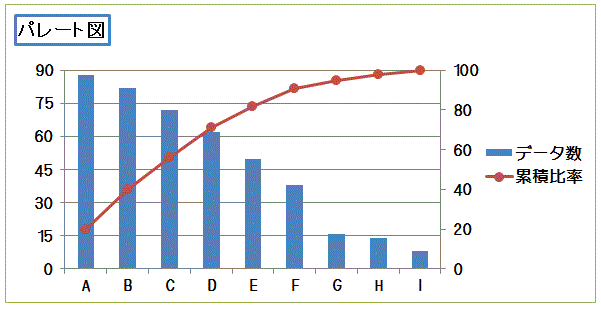
 ABC����
ABC����
�u�d�_���́v�Ƃ��Ă�A��R������̂����đ厖�Ȃ��̂��珇�ɕ��ׁA�v���C�I���e�B�����ĊǗ����Ă������Ƃ�����̂ŁA�o�c�̂�����ʂŊ��p�ł���L�͂ȊǗ���@
���80�����߂�O���[�v��A�Q�A80�`90���̃O���[�v��B�Q�A�c��̃O���[�v��C�Q�ɕ����č��ڂ̏d�v���͂���
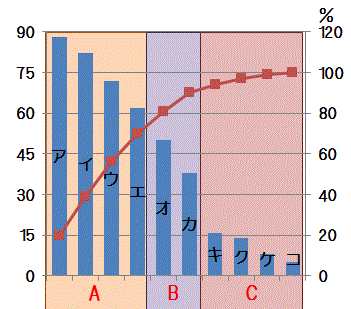
 �U�z�}
�U�z�}
�f�[�^�̎���2��ނ̓������c���Ɖ����ɂƂ�A�O���t��ɓ_�ŕ\���}
�f�[�^������(���݂��̊W)�ׂ邱�Ƃ��ł���
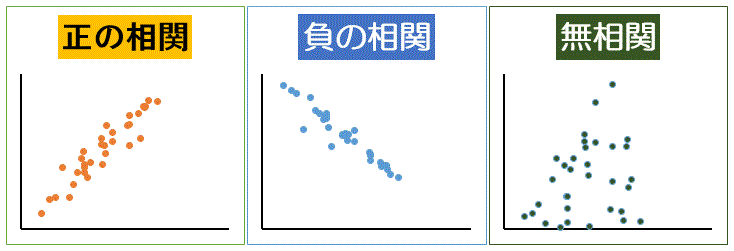
 ���ِ��v���}
���ِ��v���}
����(���ʂ̗ǂ������A�������ׂ��ۑ�)�ƁA����ɉe����^���邳�܂��܂��v���̊W���n���I�E�K�w�I�ɐ��������}�B�������͂�����ƍi�荞�܂�Ă���Ƃ��A�����h�~���邽�߂̊Ǘ����ڂ�����������A����������Njy�����肷�邽�߂Ɏg����
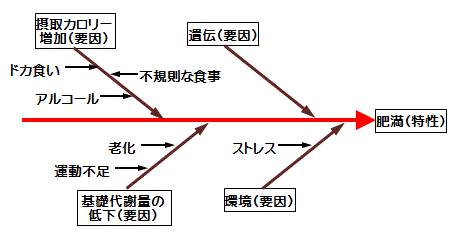
 �`�F�b�N�V�[�g
�`�F�b�N�V�[�g
�_�����鍀�ڂȂǂ�\�ɂ��āA�ȒP�ɕ��͌��ʂ��m�F�ł���悤�ɕ\��������
 �Ǘ��}
�Ǘ��}
�i������H��������ȏ��Ǘ�����Ă����Ԃɂ��邱�Ƃf�������߂Ɏg�p���邮��ӂ̂��ƁB���Ԃ��Ƃ̏�Ԃ��O���t��ɔz�u���A�]���܂łɌX���ƈقȂ�f�[�^��Ǘ����E������E�����f�[�^�̗L������ȏ�̔����肷��
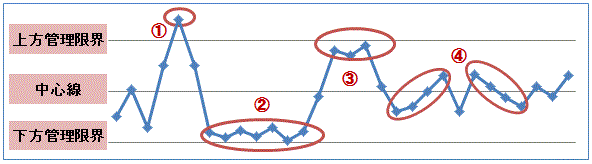
| �ُ�ȓ_�̔��f� �@�@����܂��͉����̊Ǘ����E�̊O���Ɍ����_ �@�A���S���̕Б��ɁA7�_�ȏ�̓_���A�����Č�����ꍇ �@�B�_���Ǘ����E���ɂ����Ă��A���S������2/3�ȏ㗣�ꂽ�Ƃ���� �@�@�A������2/3�_�ȏ゠��Ƃ� �@�C�_��������܂��͉������ɂȂ���B�܂��́A�����I�ɏ㉺���� |
 �w��
�w��
���W�����f�[�^�⒲�����ʂ�������Ƃɕ��ނ��āA�\�������́B�q�X�g�O�����̋�Ԃ킯���w�ʂ̂ЂƂ�
�VQC7����
 �֘A�}
�֘A�}
�ړI�E�˂炢��B�����邽�߂̉�����������o���A���邢�͍l�Ă��邽�߂ɁA�ړI�B���Ɋ֘A������_�����ʊW�Ő�������}
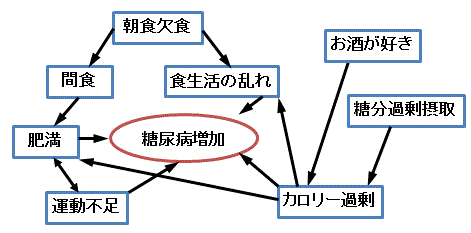
 �n���}
�n���}
�������������i�������邽�߂ɁA�ړI�|��i�̘A�����K�w�I�ɕ\�������@
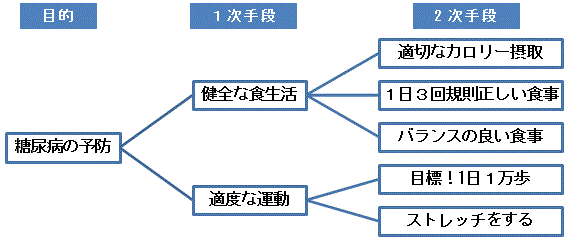
 �e�a�}
�e�a�}
�����������_��A�܂Ƃ܂��Ă��Ȃ��ӌ���A�C�f�A�Ȃǂ����A�܂Ƃ߂邽�߂ɗp������}
��}�ɂ͂܂��A�A�C�f�A�A�ӌ��A���_���Ȍ��ɕ\�����A�J�[�h�ɋL�q���A�S�̂߁A�e�a���̂���J�[�h���ăO���[�v���쐬���A��������ǂݎ���{���I�Ȗ��_������
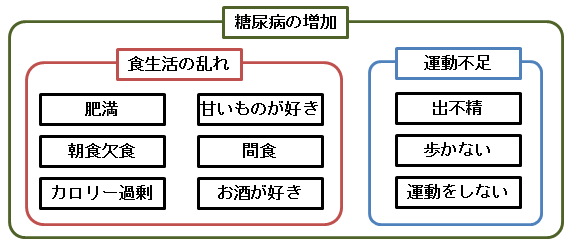
 PDPC(�ߒ�����v��})
PDPC(�ߒ�����v��})
�v������{���Ă��������ŁA�\�����ʃg���u����h�~���邽�߂Ɏ��O�ɍl������l�X�Ȍ��ʂ�\�����A�v���Z�X�̐i�s���ł��邾���]�܂��������ɓ������@
 PERT�}(�A���[�_�C�A�O����)
PERT�}(�A���[�_�C�A�O����)
�C�x���g��v���W�F�N�g�̍�Ɠ����Ȃǂ��A��Ƃ̊J�n����\���m�[�h(�����_)�ƃm�[�h�Ԃ������Ō��сA�S�̂̍�Ɠ������Ǝ��Ԃ��������悤�ɂ������́B���s���č�Ƃ���s���ŁA�ł���Ǝ��Ԃɗ]�T�̂Ȃ��H���ɉe����^����o�H���N���e�B�J���p�X�Ƃ���
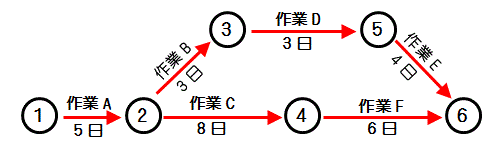
 �}�g���b�N�X�}�@
�}�g���b�N�X�}�@
���ڂ��ƂɎ��o�����f�[�^��\�Ŕ�r���邱�ƂŁA���݂��̊֘A��D��ׂ邱�Ƃ��o����}�ōł��D�ꂽ��i�����肷�邱�Ƃ��o����
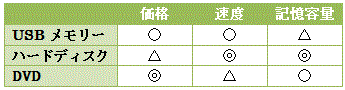
 �}�g���b�N�X�f�[�^��͖@
�}�g���b�N�X�f�[�^��͖@
�}�g���b�N�X�}�łȂ����f�[�^�����l�ł���ꍇ�A���W�����g���Čv�Z�������l�ɂ���āA�_�O���t�Ƃ��Ă�蕪����₷���\����
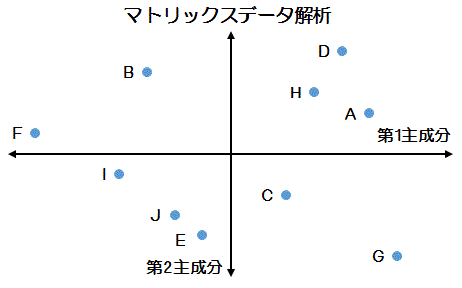
������@
�����������i�̕i�������������@�ɂ̓T���v�����O�ƃV�~�����[�V����������
 �T���v�����O
�T���v�����O
�T���v�����O�Ƃ́A������茟���Ƃ������A��W�c���炢�����̕W�{�����o���āA�s�Ǖi��X�ȉ��Ȃ獇�i�AX�{1�ȏ�Ȃ�s���i�Ƃ���B������茟���̌��ʂ́uOC�Ȑ��v���g���ĕ��͂���
 �V�~�����[�V����
�V�~�����[�V����
�쐬�������f�������A�����̌��ʂɂ��߂����ʂ邱�Ƃɂ��A���̌��ʂ�������ɖ𗧂Ă邱��
�����`�v��@(LP�@)
�@�ꎟ���ŏ����ꂽ��������̉��ōœK�����s�����ƁB�P�̖@(�V���v���b�N
�@�X�@)�A���_�@�Ȃǂ̃A���S���Y��������
�@���p��Ƃ��āA�h�{�o�����X�̏��������Ȃ���ŏ���p�̌������l�����
�@���Ȃǂɗp������
���҂��s�_
�@�ڋq���T�[�r�X���邽�߂ɍs��ɕ��Ԃ悤�Ȋm���I�ɋ������邵���Ăނ�
�@���G���ۂ��A�������f����p���ĉ�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ������_
���v�\��
�����̎��v��\�����邱�ƂŁA���̌��ʂ����ƂɎ��v�Ɍ��������Y�\�͂���������B��\�I�Ȏ�@�ɂ́A�u�ړ����ϖ@�v�Ɓu��A���́v������
 �ړ����ϖ@
�ړ����ϖ@
�ߋ��̔���̈ړ����ς��Z�o���ď�����\�������@
 ��A����
��A����
�\���E�v�����͓��ɗp������B�Ⴆ�A�ߋ��̐��Y�ʂƐ�����p�̃f�[�^�����A�������߁A�����̐��Y�ʂɑ��鐻����p�̗\���Ɋ��p�����
���̑��̎�@
�f�[�^���W
 �u���[���X�g�[�~���O
�u���[���X�g�[�~���O
���[���ɏ]���ăO���[�v�ňӌ����o���������Ƃɂ��A�V���ȃA�C�f�A�ݏo���A����������o�����@
| ���[�� | ���e |
|---|---|
| �ᔻ�֎~ | �l�̈ӌ��ɑ��Ĕᔻ������A��]�����肵�Ȃ� ���R�ȃA�C�f�A���o�𐧌�����悤�Ȕ��f�E���_�͐T�� |
| ������ | �Z���Ԃɂł��邾�������̈ӌ����o��悤�ɂ���B �ʂ͑����قǎ��̗ǂ�����������\�������� |
| ���R�z�� | �����T�O��Œ�ϔO�ɂƂ��ꂸ�A���R�ɔ����ł���悤�ɂ��� �����e�[�}����E�����Ă��A���̒��ɃA�C�f�A���B��Ă��邱�Ƃ����� |
| �������P | �A�C�f�A�ƃA�C�f�A������������A���l�̃A�C�f�A�𗘗p���ĉ��P�����肷��B �V���ȃA�C�f�A���n�o����邱�Ƃ����҂ł��� |
�|�C���g��
| ���l���́A5�`8���A�����Ă�10�����x ���Q���҂͓����悤�ȊK�w�ŏ㉺�W�����A���R�Ȉӌ����o���₷������ ���ꏊ�̓����b�N�X�ł���悤�Ȋ��ōs�� �����[�_�[�́A���낢��ȃA�C�f�A��ӌ����o�镵�͋C����� ��1���Ԉȏ㑱����Ƃ��́A�x�����Ƃ� |
 �f���t�@�C�@
�f���t�@�C�@
�����N���肤�鎖�ۂɊւ���\�����s�����@�B�Z�p�J���헪�̗��Ăɗ��p����A�����̐��ƂɓƎ��̌������o���Ă��炢�A�����𑊌݂Ƀt�B�[���h�o�b�N���čĂь������o��������Ƃ��J��Ԃ��B���v�I�Ɉӌ����W��E���������A���m�̖��ɑ��Č��ʂ��𗧂ĂĂ���
 �o�Y�Z�b�V����
�o�Y�Z�b�V����
���l���̃O���[�v�ɕ�����āA���[�_�[�̐i�s�̂��ƂɃe�[�}�ɂ��ē��c���A�O���[�v���ƂɌ������܂Ƃ߂ĕ����铢�c�̋Z�@
�f�[�^����
 �N���X�^����
�N���X�^����
���݂��������̂��W�߂ăO���[�v���������āA�S�̑���c�����镪�͎�@
 �����e�J�����@
�����e�J�����@
������p�����V�~�����[�V���������x���s�����Ƃɂ��ߎ��������߂�v�Z��@
 ���[�_�`���[�g
���[�_�`���[�g
�������ڂ̔�r��o�����X��\������O���t�̂��ƁB3�ȏ�̍��ڂɑΉ�������ː��̊e����ɁA��l�ɑ���x�������v���b�g���A�e�X������őS�̂̃o�����X������