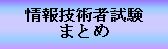企業と法務(1)
企業活動
経営・組織論
 CSR
CSR
企業の社会的責任
●コンプライアンス(法令遵守)
●コーポレートガバナンス(企業統治)
●ディスクロージャ(情報開示)
 SRI
SRI
社会的責任投資
企業の社会的責任(CSR)の状況を考慮して行う投資のこと
社会的責任の評価基準の例としては、法令順守、労働等組織内の問題だけでなく、環境、雇用、健康・安全、教育、福祉、人権、地域等さまざまな社会的問題への対応や積極的活動が挙げられている
 コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンス
企業の経営を律する枠組みのことで、企業統治とも呼ばれる。コーポレートガバナンスでは、株主などが経営者の不正を監視することで、企業の不祥事を未然に防ぐことができるとされている
 IR
IR
上場企業が株主や投資家に対し、投資判断に必要な情報を提供すること
 BCP
BCP
企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続、早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取りきめておく計画
 BCM
BCM
BCPの策定、運用、訓練、継続的改善の取組み
 組織設計
組織設計
| 1.専門化の原則 | 特殊化された役割に分割された状態によって業務に集中 |
| することで業務の専門性を上げる。業務の専門性効率を 上げて、顧客価値を上昇し収益を上げるための原則 | |
| 2.権限責任一致の原則 | 権限の大きさは職務に相応し、同時に等量の責任が負わ |
| されなければならない | |
| 3.統制範囲の原則 | 1人の管理者が直接管理できる部下の数には限界があり、 |
| これを超えると管理効率が低下する | |
| 4.命令統一性の原則 | 職位の上下関係において、各組織構成員は常に特定の |
| 一人の命令だけを受けるようにしなければならない | |
| 5.例外の原則 | 上司は日常反復的に業務処理を下位レベルの者に委譲 |
| し、例外的な業務に専念すべきである |
ゲームの理論
政治や経済など社会における人間の活動全般において、利益を最大に増やす方法、負ける場合であっても損失を最小限に食い止めるかを体系的にまとめた理論
マクシマックス原理
各戦略の最大利益を比較し、最大の利益をもたらす戦略を採用する
(例)最大利益:A=5、B=7、C=10 ⇒ 戦略Cを選択
| 状況 | x | y | z |
|---|---|---|---|
| 戦略A | 2 | 3 | 5 |
| 戦略B | 4 | 1 | 7 |
| 戦略C | 10 | 8 | -5 |
マクシミン(ミニマックス)原理
各戦略の最小利益を比較し、最大の利益をもたらす戦略を採用する
(例)最小利益:A=2、B=1、C=−5 ⇒ 戦略Aを選択
| 状況 | x | y | z |
|---|---|---|---|
| 戦略A | 2 | 3 | 5 |
| 戦略B | 4 | 1 | 7 |
| 戦略C | 10 | 8 | -5 |
ラプラス原理
すべての状況の発生確率が同じと考え、期待利益の大きい戦略を採用する
(例)x、y、zは1/3の確率で発生すると考え
期待利得:A=3.33、B=4、C=4.33 ⇒ 戦略Cを選択
| 状況 | x | y | z | 期待利得 |
|---|---|---|---|---|
| 戦略A | 2 | 3 | 5 | (2+3+5)×1/3=3.33 |
| 戦略B | 4 | 1 | 7 | (4+1+7)×1/3=4 |
| 戦略C | 10 | 8 | -5 | (10+8+(-5))×1/3=4.33 |
マクシマックス・リグレット原理
それぞれの状況における最大の利益と、各戦略で得られる利益との差を求め、その差の最大値が最小となる戦略を採用する
(例)状況x、y、zにおける最大の利得と各戦略で得られる利得の差(リグレット)を
求め、最大のリグレットの最小を求める A=8、B=7、C=12 ⇒ 戦略B
| 状況 | リグレット | 最大の リグレット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | y | z | x | y | z | ||
| 戦略A | 2 | 3 | 5 | 10-2=8 | 8-3=5 | 7-5=2 | 8 |
| 戦略B | 4 | 1 | 7 | 10-4=6 | 8-1=7 | 7-7=0 | 7 |
| 戦略C | 10 | 8 | -5 | 10-10=0 | 8-8=0 | 7-(-5)=12 | 12 |
 OC曲線
OC曲線
採用している抜取検査方式において、ある不良率をもったロットがどの程度の確率で合格するかを判断する
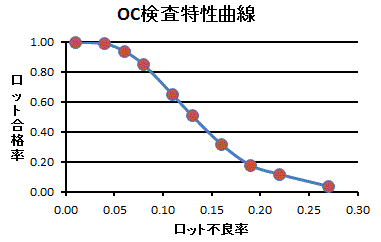
 Zグラフ
Zグラフ
折れ線グラフの一種で、「推移」を表現する。主に経営分析のツールとして利用される。一定期間の売上実績や起業の業績動向の分析に適している
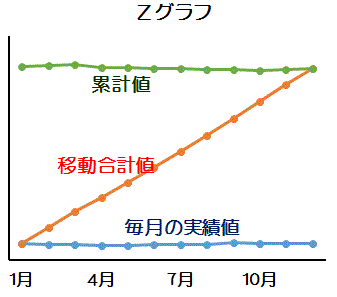
 パレート図
パレート図
分析対象のデータ(項目)を大きい順に並べた棒グラフとその累積比率を折れ線グラフで表した図。主な原因を識別するために用いる
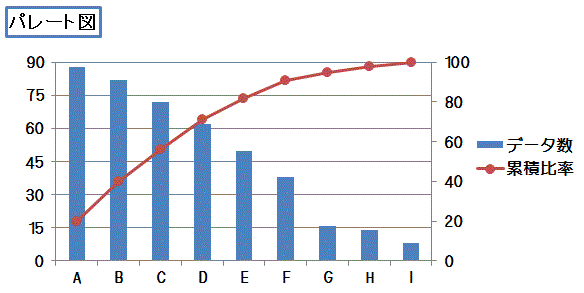
在庫管理
定量発注法(発注点方式)
発注量が一定で、発注時期は不定。在庫が決められた発注点以下になった場合に、決められた最適な発注量(経済的発注量)を発注する
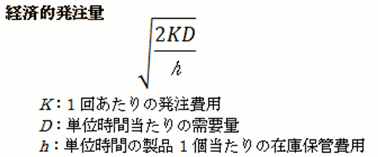
定期発注法
発注時期が一定で発注量は需要予測を行い計算する方法。種類が少なく、単価の高い商品に適用
2棚法(2ビン法)
2つの棚に商品を準備し、片方の棚から使用し始め、一方の棚が無くなった時点で発注を行う方法