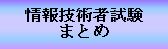���Z�L�����e�B�}�l�W�����g(5)
�����I�Z�L�����e�B
�ЊQ�E��Q�̑�
ISMS�̗v������
�Z�L�����e�B��ۂׂ��̈�
�����⎷���������̎{�݊W�Ɋւ��镨���Z�L�����e�B�̊Ǘ���
 �����I�Z�L�����e�B���E
�����I�Z�L�����e�B���E
�����I�ɕی삵�Ȃ�������Ȃ��G���A���m�F���A���̃G���A�ɓK�ȕ����I���E�i�ǁA�J�[�h���䓙�j��݂��邱�Ƃ����߂���
�u�Z�L�����e�B���E�v�Ō��肵�����E�����ƂɊe�G���A�ւ̓K�ȕ����v�����߂���
 �����I���ފǗ�
�����I���ފǗ�
�����������Ă���҂����������ł���悤�ɂ��邽�߂̊Ǘ���ɂȂ�A���ޏo�Ɋւ���Ǘ����@�����߂���
 �I�t�B�X�A�����y�ю{�݂̃Z�L�����e�B
�I�t�B�X�A�����y�ю{�݂̃Z�L�����e�B
�I�t�B�X��{�݂ɑ��Ă̐v�w�j���w�������A���̂Ƃ���������邱�Ƃ����߂���
��̓I�ɂ́A��ʂ̐l���A�N�Z�X�ł��Ȃ��悤�ȏꏊ�̐ݒu��O�����猩�����ɂ��̎{�݂����̎{�݂��킩��Ȃ��悤�ɂ���Ȃǂ̐v�w�j���߁A���̒ʂ蕨���v���Ă�������
 �O���y�ъ��̋��Ђ���̕ی�
�O���y�ъ��̋��Ђ���̕ی�
�O���i�\�͍s�ד��j�y�ъ��i���R�ЊQ�j������ׂ���Y��ی�ł���悤�����v���s�����Ƃ����߂��Ă���A�v�w�j�̍���ɂȂ�
 �Z�L�����e�B��ۂׂ��̈�ł̍��
�Z�L�����e�B��ۂׂ��̈�ł̍��
�ʏ�̎{�y�уI�t�B�X��Ƃ̂Ȃ��ł����ɏd�v�ȁA�����Z�L�����e�B���x����ۂK�v������Ɩ��ɂ��āA���̃Z�L�����e�B���x�����ێ����邽�߂̕����I�Ȏw�j�����āA�v���邱�Ƃ����߂���
 ��ʂ̐l�̗������ꏊ�y�юn���ꏊ
��ʂ̐l�̗������ꏊ�y�юn���ꏊ
�X�֎�ו��̎n���ꏊ���̈�ʂ̐l�����R�ɗ�������ꏊ�ɑ��镨���ʂ̎w�j�����āA�v���邱�Ƃ����߂���
��j��ʂ̐l�̗������ꏊ�F������Ƃ������Ă��錚�����̗X�֎�ו��̔z���ꏊ��A�܂��S�~�̏W�Ϗ��Ȃ�
���u�̃Z�L�����e�B
���u�n�̊Ǘ���Ŏ�ɋ@��̕����ʂɊւ���Ǘ���
 ���u�̐ݒu�y�ѕی�
���u�̐ݒu�y�ѕی�
���u�i�T�[�o�Ȃǁj�ɑ��čЊQ��s���A�N�Z�X����̋��Ђ�ጸ���邽�߂̑��߂���
 �x�����[�e�B���e�B
�x�����[�e�B���e�B
���u�̉ғ����ێ����邽�߂̓d�C�A�����A�Ȃǂ��������@�\����悤�ɊǗ����邱�Ƃ����߂���B �����ł́A����������펞�̑Ή��A�璷���Ȃ�
 �P�[�u���z���̃Z�L�����e�B
�P�[�u���z���̃Z�L�����e�B
�ʐM�P�[�u���y�ѓd���P�[�u���̒f����s�����p����ی삷�邱�Ƃ����߂���
��ʓI�Ȃ̂��A���[���ŕی��s�v�ȃP�[�u���̓P�p�A�d���P�[�u���̎g�p�����̃`�F�b�N
 ���u�̕ێ�
���u�̕ێ�
���ږ��̂Ƃ���K�ɕێ炷�邱�Ƃ����߂���B�K�p����鎖�Ƃ�X�N�̊�ɓK�ȕێ�̐����m�����邱�Ƃ��K�v
 �\�O�ɂ��鑕�u�̃Z�L�����e�B
�\�O�ɂ��鑕�u�̃Z�L�����e�B
�\�O�ł́i�@�킾���łȂ��}�̂��܂ށj���u�̗��p�ɂ�����A�����E����Ȃǂ̃Z�L�����e�B���X�N�ɑ�����߂���
 ���u�̈��S�ȏ������͍ė��p
���u�̈��S�ȏ������͍ė��p
�������������u��ė��p�̑��u����̏��R�k��h�����߂̓K�ȏ��u�i���u�ɕۑ������f�[�^�̍폜��\�t�g�E�F�A�̏�����)�����߂���
 ���u�̈ړ�
���u�̈ړ�
����ȍ\�O�ւ̑��u�i����\�t�g�E�F�A���܂ށj�̎����o����h�����߂���
�ݔ��ʂ̑�
��p���^��p���ւ̐ݒu
�d���A�Ȃǂ��������ꂽ���̃T�[�o����݂��A�d�v�ȃT�[�o��@���ݒu����
�n�k��
- �T�[�o���͍Œ��1981�N�����̌��z��@���K�p���ꂽ�ϐk�\���̌������ɐ݂���
�i2000�N����̌��z��@�f���������������]�܂����j - ���u�n�ɕK�v�Ȑݔ������������o�b�N�A�b�v�Z���^��ݒu����
- �T�[�o��@��ނ́A�]�|�^�����h�~�Ȃǂ̒n�k�{���ꂽ���b�N�Ɏ��[����
�d����Q��
CVCF�AUPS�A�o�b�N�A�b�v�o�b�e���A���Ɣ��d���u�ȂǂŁA��d�A�u���d���ቺ�A�d���ϓ��A���g���ϓ��Ȃǂ̓d����Q�ɑς���
��
�T�[�o�ނ̐���ғ��Ɖ^�p�v���̌��N�ʂɔz�������K�Ȏ������ێ��̂��߁A�ݔ�������
�Б�
�s�������K�X�Ȃǂɂ����ΐݔ��A�h�ΕǁA���T�m�@�Ȃǂ�����
�����Q��
- �\���ȉ���e�ʂ��m�ۂ���
- �����̒ʐM���Ǝ҂ƌ_�A�قȂ郋�[�g�ł̃o�b�N�A�b�v���������
���̑�
�R���A�Z���A�����A�Ód�C�A�m�C�Y�A�����Ȃǂւ̑���s��
 CVCF
CVCF
�d���Ǝ��g�������肵����Ԃɕۂ��A�d���̈��苟�����s�����u
 UPS�i����d�d�����u�j
UPS�i����d�d�����u�j
��d�E�u���d���ቺ�E�d���ϓ��E���g���ϓ��Ȃǂ̓d����Q����n�[�h�E�F�A����鑕�u�B����d�d�����u
�^�p�Ǘ���̗��ӓ_
- �e�ݔ��̊Ǘ��҂m�ɂ���
- �e�ݔ��̒���_���A�ێ���m������
- �ЊQ���Q�������̑Ή��菇��A���̐��m�ɂ��Ă����B�Ή��P�������{����
IDC�̊��p
�������ʂ̑������������ւ̉�����Ƃ��ăT�[�o�֘A�ݔ���IDC�ւ̃A�E�g�\�[�V���O�����ڂ���Ă���
 IDC
IDC
�C���^�[�l�b�g�ڑ��ɓ��������ݔ��E�T�[�r�X����鎖�Ǝҋy�ь����̂���
���x�ȃZ�L�����e�B��ЊQ�ϐ����������ꂽ�������ɁA�l�b�g���[�N�@��E�T�[�o��f�[�^�Ȃǂ�ݒu�E�ۊǂ�����S�ȏꏊ�����Ƌ��ɁA�C���^�[�l�b�g�ڑ��Ȃǂ̊e��ʐM�Ԃւ̃A�N�Z�X�C���t���Ԃ����B�܂��A�ʏ�͉^�p��Ď��Ɩ��Ȃǂ������Ɉ����A��Q�������̒ʒm��Ώ��ȂǃV�X�e���^�p�̃T�|�[�g���s���̂��A��̓I�ȃT�[�r�X
IDC�ɋ��߂���v��
 ���n����
���n����
�n�k���̍ЊQ�ɂ��IDC���g����Q���T�[�r�X����~����悤�Ȏ��ԂɊׂ�Ȃ����߂́AIDC�̏��݂Ɋւ�������̂���
- �n�k�ɂ���Q�̋���̏��Ȃ��n���ł��邱��
- ���y��ʏȂ⎩���̂����J���Ă���n�U�[�h�}�b�v���̏��Ŋ댯�n��Ǝw�肳�ꂽ�ꏊ�ɂȂ�����
- �Ôg�A�����A�W�����J���ɂ��o���̊댯�����w�E����Ă��Ȃ��n��ł��邱��
- ���a100m�ȓ��ɏ��h�@�ɂ�����w�萔�ʈȏ�̊댯�������{�݂⍂���K�X�����{�݂��Ȃ�����
- ��Q�����̍ۂɁA�@�퓙�̕ێ�Ǝ҂̃T�|�[�g���_����30���ȓ��ŃA�N�Z�X�\�ł��邱��
 �{�݁E�}�V�����[������
�{�݁E�}�V�����[������
�{�ݏ����́A�ϐk���̌����̍\����ʐM�ݔ����̓�d���Ƃ����������̂��Ƃł���A�}�V�����[�������Ƃ́A���b�N�E�@���ݒu������Ɋւ�������̂��Ƃł���
- �����\�����k�x6���ɑς�����ϐk�A���邢�͖Ɛk���̍\��������Ă��邱��
- ���z��@�y�я��h�@�ɓK�������Е�m(�h��)�V�X�e�����ݒu����Ă��邱�ƁB���z��@�y�я��h�@�ɓK�������Е�m(�h��)�V�X�e���A���邢�͎������̕ω���q���Ɏ@�m���З\�������m�ł���V�X�e�����ݒu����Ă��邱��
- ���ΐݔ��́A���Ύ��̐��Q�A���тɊ��ی���l�������I�]���w�j��W�����[���ł���K�X�n���ΐݔ��Ƃ��邱�ƁB�������́A���ΐݔ��́A���Ύ��̐��Q�A���ی�A���тɐl�̂ւ̉e�����l�����A���f���ΐݔ��Ƃ��邱��
- ���o�H���m�ۂ���ϓ_�ŁA�����ւ̏o�������2�ӏ��ȏ�݂��Ă��邱�ƁB�܂��A���b�N�A�@�퓙�̔��o���̂��߂̃G���x�[�^���ݒu����A24 ���ԁ~7 ���ԁ^�T���p�\�ł��邱��
- �ʐM����ɂ��ẮA����̒ʐM���Ǝ҂Ɉˑ����Ȃ��o�H�̈قȂ���2�n���ȏ�̉���̈����������ł��邱��
- �}�V�����[���͖����Ƃ��铙�A�O��������������ʂ��Ȃ��\���Ƃ��邱��
- �}�V�����[���̃t���[�A�N�Z�X�́A�ő�����x500gal �ȏ�ɑς����邱�ƁB�������A�Ɛk�\���̏ꍇ�͌����������͖Ɛk���u�E�������Y�����x�ȏ�ɑς����邱��
- �}�V�����[���̓V�䍂�̓t���[�A�N�Z�X����������2,400mm �ȏ�ł��邱��
- �}�V�����[���̃t���[�A�N�Z�X�̏��d�́A�ʓr���B�����@��y�ы@�퓋�ڌ�̃��b�N�̏d��600kg/�u�ȏ�ɑς�����\�͂�L���Ă��邱��
- �}�V�����[���́A�h�������Ă��邱��
- �Z�L�����e�B�Ǘ���A�ق���IDC ���p�҂ƍ��݂��Ȃ��Ɨ�����������邱�ƁA���邢�͂ق���IDC ���p�҂ƍ��݂��Ȃ��悤���b�N�P�ʂɎ{���ł��邱��
- �ʓr���B����郉�b�N�A�@�퓙�̏����\�ɋL�ڂ���ݒu��(�@�\)����邱�ƁB
 �d���E����
�d���E����
�d���E�����́A�d���E�ݔ��̓�d���Ƃ������璷���m�ۂɊւ�������̂��Ƃł���
- ��d�ݔ��͖@��_���������S����~�ł��邱��
- ����d�d�����u(UPS)���d������g�����u(CVCF)�A���Ɣ��d���u������Ă������ƁB�܂��A���d�ݔ��g�p�����R���⋋�ɂČp���^�]���\�Ƃ��A���S����~�ł��邱��
- 2�n���ȏ�̋��d�o�H�E�����ɂēd���̈������݂�}��A�{�ݓ��͓�d�����̏璷�����m�ۂ��Ă��邱��
- ��d�����̏璷�����m�ۂ����ݔ���L���Ă��邱�ƁB�܂��A�ЊQ���ɒf���ƂȂ��Ă�24���Ԉȏ�A�����ĉ^�]�\�ȋݔ��ł��邱��
- �ʓr���B����郉�b�N�A�@�퓙�̏����\�ɋL�ڂ���d���ݔ�(�@�\)����邱��
- �ʓr���B����郉�b�N�A�@�퓙�̏����\�ɋL�ڂ���ݔ�(�@�\)����邱��
 �Z�L�����e�B����
�Z�L�����e�B����
�Z�L�����e�B�����́A�����I�Z�L�����e�B�Ɋւ������
- �����ւ̓��قƃ}�V�����[���ւ̓����ɌW��Z�L�����e�B�F�؋@�\�����ꂼ��Ɨ������d�g�݂ł��邱�ƁB�܂��A�����̓�����ɂ����ėL�l�x�����܂ރZ�L�����e�B�{����Ă��邱��
- �N�����m�Z���T�[�A�Ď��J�����A���ގ��Ǘ��V�X�e�����ɂ��@�B�x���V�X�e������������Ă��邱��
- �풓�x�������͋@�B�x���V�X�e�����ɂ����ފǗ���24 ���ԁ~7 ���ԁ^�T�A����Ă��邱��
- IDC ���̓�ISO/IEC 27001 �ފǗ������Ƃ��āAIC�J�[�h��̔F�ؑ��u���̖{�l�m�F���u��L����ƂƂ��ɁA�Ď��J���������p����T�[�o���[�����ɐݒu����Ă��邱��
 �^�p����
�^�p����
�^�p�����́AIDC�E�ݔ��̈ێ��E�Ǘ���ƂɊւ������
- IDC�E�ݔ��ɌW��24 ���ԁ~7 ���ԁ^�T�̊Ǘ��̐��������ƂƂ��ɏ�Q���̎t���E�A���������J�݂��Ă��邱��
- IDC�E�ݔ��̒���_�������{���Ă��邱��
���Z�L�����e�B��̊ϓ_����A���m�ȏ��ݒn�����J�Ƃ��Ă��鎖�Ǝ҂�����
| ���� | IDC | ��ʃI�t�B�X |
|---|---|---|
| ���p���� | 24����365�� | �ʏ�͕����A�A�J���� |
| �ϐk�E�Ɛk | �ʏ�{�t�����l | �ʏ� |
| ���d | 700kg/ m2�ȏ� | 300 kg/m2 |
| �K�� | 3.5�`4.5�� | 3.7��4.1m |
| ��d�� | 500mm�ȏ� | 0�`500mm�ȏ� |
| ��d���@ | �X�|�b�g�l�b�g���[�N���� | �ʏ� |
| ��d�e�� | 750VA/m2�ȏ� | 40�`50 VA/m2 |
| ���Ɣ��d | �T�[�o�G���A��d�e�ʈȏ�A24���� | �h�Зp�A�Z���� |
| ����d���u | ���Ɣ��d����ғ��܂ł̓d�͋��� | �Ȃ� |
| �� | �����o���A24���ԉғ� | �ʏ� |
| ���ΐݔ� | �V�K�X���Ȃ� | �X�v�����N���[ |
| �ʐM��� | 2�n���@�����ƎґΉ� | �ʏ� |
�s���s�ׂւ̑�
�����Ȃǂ̃A�N�Z�X�Ǘ�
�����ւ̃A�N�Z�X�Ǘ��̎��
| �E���ގ��̊Ǘ� | �F | IC�J�[�h��̔F�𗘗p���A�����ꂽ�l�ȊO�͓��ގ����ł��Ȃ��d�g�݂ɂ��� |
| �E�{���Ǘ� | �F | �����ꂽ�ꍇ�ȊO�͏�Ɏ{������ |
| �E���ގ��̋L�^�̕ۑ� | �F | ���ގ��̋L�^���Ƃ�A�N�������ގ���������ۑ����� |
| �E�Ď��J���� | �F | �Ď��J�����ɂčs�����Ď�����ƂƂ��ɁA�L�^��ۑ����� |
�Ǘ��K��
 �V�X�e���\��
�V�X�e���\��
���ގ��J�[�h�A���ގ��J�[�h�ǎ摕�u�A�w��F�ؑ��u(�h�A�p)�A�w��o�^���u�A���ގ��Ǘ��T�[�o�A�d�C���A��t�d�b�AUPS����\�������
�w��F�ؑ��u�́A���ގ��J�[�h�ǎ摕�u�ƕ��ׂāA���O(�����p)�Ǝ���(�ގ��p)�ɐݒu����
 �w��o�^
�w��o�^
�w��o�^���u��p���āA�C�ӂ�2�w���o�^����
 �o�^���ꂽ�w��f�[�^�̍폜
�o�^���ꂽ�w��f�[�^�̍폜
�ٓ���ސE�ɘA�����č폜�����
 �d�C���̊J��
�d�C���̊J��
�w�䂪�F���ꂽ�ꍇ�ɉ������A�h�A���܂�����{������B������Ƀh�A���J����Ȃ������ꍇ�́A��莞�Ԍ�Ɏ����I�Ɏ{�������
 ���ގ��Ǘ��T�[�o�̃��O
���ގ��Ǘ��T�[�o�̃��O
���ގ������l�����ł��郍�O���A������ԕۑ�����
 ���K�ґΉ�
���K�ґΉ�
��t�d�b�ɂ���Ď����ɂ���Ј�����������B�Ή��҂́A�K���҂̓�������ގ��܂ł̊ԕt���Y��
 �Ď��J�����Ƃ̘A�g
�Ď��J�����Ƃ̘A�g
���ގ��摜���L�^���A������ԕۑ�����B�f�[�^�Z���^�ɂ����ẮA�����̉摜���L�^���A������ԕۑ�����
�Z�L�����e�B���
�I�t�B�X������3�̋��ɕ��ނ��ĊǗ�����B
| ��ʋ�� | �F | �Ј��ȊO�̎҂ł����Ă����ʂȐ��������ɓ����\�ȋ�� |
| �Ɩ���� | �F | �Ј��y�юЈ��̋����҂����������\�ȋ�� |
| �A�N�Z�X������ | �F | ���̊Ǘ��ӔC�҂ɂ���ċ����҂����������\�ŁA�����҂Ƃ��̓���������ǐՂł����� |
| ��於 | �Ǘ��K�� |
|---|---|
| ��ʋ�� | �Ј��́A��ɎЈ��𒅗p����B |
| �Ɩ���� | �E��ʋ��Ƃ͌��łȊu�ǂɂ���ċ��A��Ɏ{������ �E�Ј��́A��ɎЈ��𒅗p���� �E�Ј��ȊO�̎҂���������ɂ́A���O�ɓ����̐\�����s���������ŁA�����ے��̏��F��K�v������ |
| �A�N�Z�X������ | �E��ʋ��Ƃ͗אڂ����Ȃ� �E�Ɩ����Ƃ͌��łȊu�ǂɂ���ċ��A��Ɏ{������ �E�����̗����������I�ɋL�^���� �E�Ј��́A��ɎЈ��𒅗p���� |
�s���ȏ����W����
�\�[�V�����G���W�j�A�����O
�l�����܂��ď�����肵�A�s���ȃA�N�Z�X�����݂��@�̑���
 �Ȃ肷�܂�
�Ȃ肷�܂�
�ڋq���Г��̐l�ԂɂȂ肷�܂��āA��Ɣ閧���͂��߂�������������o�����Ƃ����@
 �X�L���x���W���O
�X�L���x���W���O
�S�~��������
 �V�����_�[�n�b�L���O
�V�����_�[�n�b�L���O
�p�X���[�h�̓��͏�����납��`������
 �t�B�b�V���O
�t�B�b�V���O
���[���ŋU��Web�T�C�g�ɗU�����AID��p�X���[�h�A�N���W�b�g�J�[�h�ԍ�����s���ɓ��͂����@
����
���p�ҋ���
���d�b�ł�ID�A�p�X���[�h�������Ȃ�
���@�������S�~���Ɏ̂ĂȂ�
�����[������̃����N�͗��p���Ȃ��Ŏ����̃����N�AWeb�T�C�g�̃g�b�v�y�[�W���烊���N�����ǂ�
���S������̂Ȃ����̍ē��͕͂K���⍇��������
�e���y�X�g�U��
�R���s���[�^����Ӌ@��A�P�[�u������R�k(�낤����)�������ȓd���g��T�A�p�X���[�h�Ȃǂ̃Z�L�����e�B����s���ɓ��肷�邱�ƁB
�l�I�Z�L�����e�B
�l�I�Z�L�����e�B��
�l�I�Z�L�����e�B��Ƃ��āC�l�ɂ����C����C�s���s�ׂ̃��X�N�Ȃǂ��y�����邽�߂̋���ƌP���C�����⎖�̂ɑ��Ĕ�Q���ŏ����ɂ��邽�߂̑�
�y��z
���Z�L�����e�B�|���V�A�Г��K���A���Z�L�����e�B����E�P���A���Z�L�����e�B�[�ցA�������̂ւ̑Ώ��}�j���A���쐬�Ƃ��̏���A�p�X���[�h�Ǘ��A�A�J�E���g�Ǘ��Aneed-to-know�A���O�Ǘ��A�Ď��A���R������A�v���C�o�V�[�}�[�N�A�Z�L�����e�B�S���ҁA��������
�Z�L�����e�B����
���Z�L�����e�B�|���V��֘A�K��̎��m�O����͂���
�Ώێ҂́A�S�]�ƈ�(�ϑ���̒S���҂��܂�)�ŁA�����������Ȃǂ��ċ��ЂƑ�ɂ��ċ��炷�邱�ƂŁA��u�҂̃��`�x�[�V���������߂�
- ����I�i1 �N�Œ�1 ��j�Ȏ��{
- �|���V�[�ύX���A�Z�L�����e�B�����E���̔�����
- ���炵�Ă��Ȃ��҂ւ̍ċ���
- ��u�̊Ǘ�
- �o�c�ҁA�Ǘ��ҁA��ʎЈ��Ȃǖ����ɉ���������
- �X�̗��p�҂ɋN���肤�郊�X�N��F�������A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����𗝉�������
�E����`����ьٗp�ɂ�����Z�L�����e�B
�l���ٓ����Ɋւ���Ǘ��K��(�A�ƋK���A�����K��Ȃ�)�̐������͂���
- �A�ƋK���ɂ́A�A�Ə�Z�L�����e�B�Ɋւ���`���A���玖���m�ɂ���
- ���`��������݂��A�Ɩ���m�肦���@�������O���ɘR�炳�Ȃ����ƂL���� �i�]�ƈ��Ƃ́A�@���ێ��_������ԏꍇ������j
- �ٗp�J�n�A�I�����̊e����Ƃ̘A���̐��̐����ƃA�J�E���g�̍폜�Ȃǂ̎菇���̐���
�h���Ј��̊Ǘ�
- �h���Ј��ɂ����Ђ̏��Z�L�����e�B�|���V�����炵�A�\���ȗ����邱��
- ���Ђ̃V�X�e���^�p��Ƃɂ����āA�A�J�E���g�Ǘ��Ɋ�Â��A�N�Z�X���O�̊Ď���d�v��Ƃɂ����闧��Ȃǂ̊Ǘ����s��
- �h���_�Ɏ��`���A�Z�L�����e�B�}�l�W�����g�̏��������炷�邱�ƂL���A���m�O�ꂳ���邱��
�Z�L�����e�B�������̂���ь듮��ւ̑Ώ�
�v���ȕ菇�̊m���ƓO��
�ϑ���̊Ǘ�
- �O���ϑ��̑Ώۂ͈̔́A�ϑ���ɂ��A�N�Z�X��F�߂��Y�̊�̐���
- �ϑ��悪������ׂ��v���Ɋւ����̐���
- �ϑ��Ɩ��Ɋւ��āA���Z�L�����e�B���N�Q���ꂽ�ꍇ�̑Ή��菇�̐���
- �ϑ���̏��Z�L�����e�B�̎��{���m�F����]����̐���
- �ϑ��_��̒����i���`���A�_��ᔽ���̑[�u�A���Z�L�����e�B�����E���̂̍ۂ̑Ή��菇�A���Z�L�����e�B�č����邱�ƂȂǁj
- �ϑ���̊ē�
- �ϑ��I�����ɂ͒��Ă���������V�X�e���̕ԋp�A�j���̊m�F